・推薦を使いたいんだけど、どんな推薦があるの?
・どんなところに注意すれば推薦入試を利用できるの?
という人のために、入試の一般選抜について解説します
00.専願と併願
専願(せんがん)と併願(へいがん)の最も大きな違いは、
合格した場合にその学校へ入学する義務があるかないかです。
- 専願: 合格したら、必ずその学校に入学します
- 併願: 合格しても、他の学校と比べて進学先を選ぶことができます
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
専願(単願)
「この学校が第一志望で、合格したら必ず入学します!」と約束して出願する方法です。
「単願(たんがん)」とも呼ばれます。
✅ メリット
- 合格の可能性が上がる場合がある: 学校側は必ず入学してくれる生徒を確保したいため、併願の受験生よりも合格ラインが少し低めに設定されたり、評価で有利になったりすることがあります。
- 受験対策に集中できる: 目標が1校に絞られるため、その学校の過去問対策などに専念できます。
- 早く受験が終わりやすい: 一般入試より早い時期に行われることが多く、合格すれば早く進路が決まり、残りの学校生活を楽しんだり、入学準備に時間を使えたりします。
- 費用を抑えられる: 受験する学校が1校で済むため、受験料や交通費などの負担が少なくなります。
⚠️ デメリット
- 合格したら辞退できない: 「もっと自分に合う学校が見つかった」「他の学校も受けてみたかった」と思っても、原則として入学を辞退することはできません。
- 不合格の場合のリスク: 専願で不合格になると、その後の一般入試などで改めて受験し直す必要があります。
併願
複数の学校を同時に受験する方法です。滑り止めや、実力を試す「お試し受験」として利用されることが一般的です。
✅ メリット
- 進学先を確保しやすい: 複数の学校を受験するため、「どこにも合格できなかった」というリスクを減らせます。精神的な安心材料になります。
- 合格した中から進学先を選べる: 複数の合格通知を手に、学費やカリキュラム、通学のしやすさなどを比較検討して、自分に最も合った学校を選べます。
- 試験の雰囲気に慣れることができる: 本命校の受験前に他の学校で試験を経験しておくことで、本番の緊張を和らげることができます。
⚠️ デメリット
- 費用がかさむ: 受験する学校の数だけ受験料が必要です。また、合格した場合、入学しない学校にも一時的に入学金を納めなければならないことがあります。
- 対策が分散しがち: 複数の学校の入試対策が必要になるため、勉強の負担が大きくなります。
- スケジュール管理が大変: 入試日程が続くと、体力・精神的にハードになります。
自分の学力や「その学校に行きたい」という気持ちの強さ、そして家族ともよく相談して、
自分に合った方法を選びましょう。
01.公募制推薦
公募制推薦(こうぼせいすいせん)とは、大学入試の選抜方法の一つで、
大学が定めた出願条件を満たし、在籍している高校の学校長から推薦をもらえれば、
どの高校からでも応募できる推薦入試のことです。
「学校推薦型選抜」という大きな枠組みの中にあり、
特定の高校の生徒しか出願できない「指定校推薦」とは対照的です。
公募制推薦のポイント
- 誰でもチャンスがある: 大学が指定した高校(指定校)でなくても、出願条件さえクリアすれば全国どこの高校生でも挑戦できます。
- 高校での頑張りが評価される: 学力試験だけでなく、高校時代の成績(評定平均)や、部活動、課外活動などの実績が総合的に評価されます。
- 選考方法は大学によって様々: 書類審査(調査書、推薦書など)に加え、小論文、面接、基礎的な学力試験などが課されることが一般的です。
- 一般選抜より早く結果が出る: 多くは秋(11月頃)に出願・試験が行われ、年内(12月頃)に合否が判明します。
公募制推薦の主な種類
公募制推薦は、主に2つのタイプに分けられます。
1. 公募制一般推薦
高校での学習成績(評定平均)を重視するタイプです。多くの大学が「全体の評定平均値が3.5以上」のように、出願の基準を設けています。日々の授業や定期テストに真面目に取り組んできた生徒が評価されやすい制度です。
2. 公募制特別推薦
学業成績だけでなく、スポーツや文化活動での優れた実績、特定の資格(英検など)、ボランティア活動などを評価するタイプです。評定平均の基準が一般推薦より緩やかであったり、設けられていなかったりすることもあります。部活動などで大きな実績を残した生徒に有利な制度です。
メリットとデメリット
公募制推薦には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
✅ メリット
- 受験のチャンスが増える: 一般選抜の前に、一度受験の機会を持つことができます。ここで合格できなくても、一般選抜で再挑戦が可能です。
- 学力試験以外の強みをアピールできる: 評定平均や部活動の実績など、ペーパーテストだけでは測れない自分の頑張りを評価してもらえます。
- 早く進路が決まる安心感: 年内に合格が決まれば、残りの高校生活を落ち着いて過ごしたり、大学入学後の準備に時間を充てたりできます。
- 一般選抜より試験科目が少ない場合がある: 2科目+面接など、一般選抜よりも対策する科目数が少ないことが多く、的を絞って準備ができます。
⚠️ デメリット
- 対策に時間がかかる: 一般選抜の勉強と並行して、小論文や面接の対策が必要になり、負担が大きくなることがあります。
- 必ず合格できるわけではない: 指定校推薦と違い、誰でも応募できるため倍率が発生し、不合格になることも珍しくありません。人気の大学・学部では高倍率になることもあります。
- 専願の場合は辞退できない: 出願時に「専願(合格したら必ず入学する)」か「併願(他の大学と検討できる)」かを選びますが、専願で合格した場合は基本的に入学を辞退できません。
公募制推薦は、高校生活をコツコツと頑張ってきた人や、
学業以外に打ち込んできたことがある人にとって、大きなチャンスとなる入試制度です。
自分の強みが生かせるかどうか、大学の募集要項をよく確認してみましょう。
02.指定校推薦
指定校推薦(していこうすいせん)とは、
大学が「この高校の生徒なら信頼できる」と判断し、特定の高校に推薦枠を与える入試制度です。「学校推薦型選抜」の一つで、主に私立大学で実施されています。
一言でいうと、「高校内での代表選考」に勝てば、ほぼ合格が約束される特別な推薦入試です。
指定校推薦の仕組み
指定校推薦は、以下のような流れで進みます。
- 大学から高校へ推薦枠の通知が来る (6月~7月頃)
- 大学が、長年の進学実績などから信頼する高校に対し、「〇〇学部から2名、△△学部から1名」といった形で推薦枠を通知します。
- 校内選考への応募 (7月~9月頃)
- 高校内で推薦枠が公開され、希望する生徒が応募します。
- 校内選考 (9月~10月頃)
- ここが最大の関門です。 希望者が推薦枠より多い場合、高校が成績(評定平均) を最優先に、部活動、生徒会活動、生活態度などを総合的に評価して、誰を推薦するかを決定します。
- 大学への出願・選考 (11月~12月頃)
- 校内選考を通過した生徒は、学校長の推薦書などを持って大学に出願します。
- 大学では、面接や小論文などの簡単な試験が課されることがほとんどです。形式的な確認の意味合いが強く、よほどのことがない限り不合格にはなりません。
- 合格発表 (12月頃)
- 年内に合格が決定します。
メリットとデメリット
✅ メリット
- 合格率が極めて高い: 高校の校内選考を通過すれば、大学の試験で不合格になることはほとんどなく、ほぼ100%合格できます。
- 早く進路が決まる安心感: 一般選抜よりもかなり早い時期(年内)に合格が決まるため、精神的な負担が少なく、残りの高校生活や入学準備に時間を有効に使えます。
- 学力試験の負担が少ない: 一般選抜のような厳しい学力試験がないため、高校の定期テストをコツコツ頑張ってきた生徒が報われやすい制度です。
⚠️ デメリット
- 校内選考が非常に厳しい: 推薦枠はごくわずか(1学部1~2名など)のため、希望者が多い場合は高校内で熾烈な競争になります。特に高校1年生からの成績(評定平均)が最も重視されます。
- 合格したら絶対に辞退できない(専願): 指定校推薦は、大学と高校の信頼関係で成り立っています。そのため、合格した場合は必ずその大学に入学しなければならず、他の大学を受験することはできません。
- 希望の大学・学部の枠があるとは限らない: 自分の高校に、行きたい大学や学部からの推薦枠がなければ、この制度を利用することすらできません。また、推薦枠は毎年見直されるため、去年あった枠が今年も来るとは限りません。
- 入学後のプレッシャー: 高校の代表として入学するため、学業不振や問題行動は許されず、後輩たちの推薦枠にも影響しかねないという責任が伴います。
指定校推薦は、高校生活3年間、授業態度や定期テストに真面目に取り組み、高い成績を維持し続けてきた生徒にとって、非常に有利な制度と言えるでしょう。
まとめ
学校推薦は専願で受験することになります。
しかし、一般選抜の方法では大きな不安がある人にとってはとても有利な制度です。
ぜひ、学校推薦型選抜を活用していきましょう。
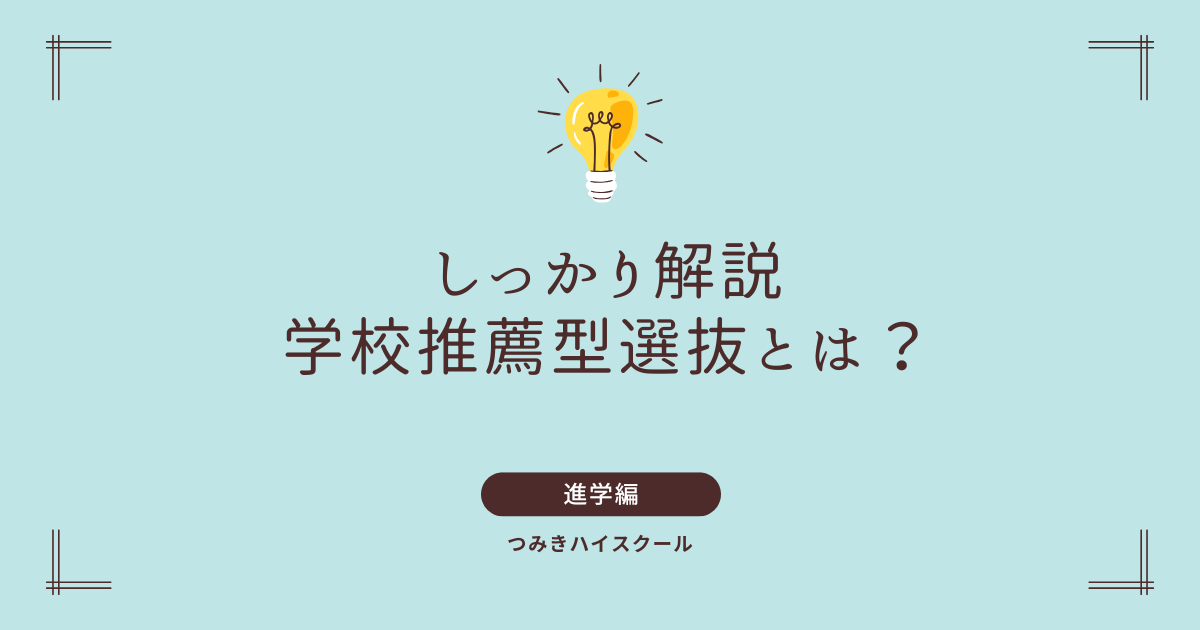
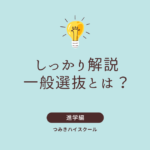
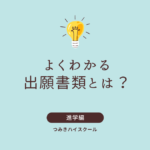
コメント